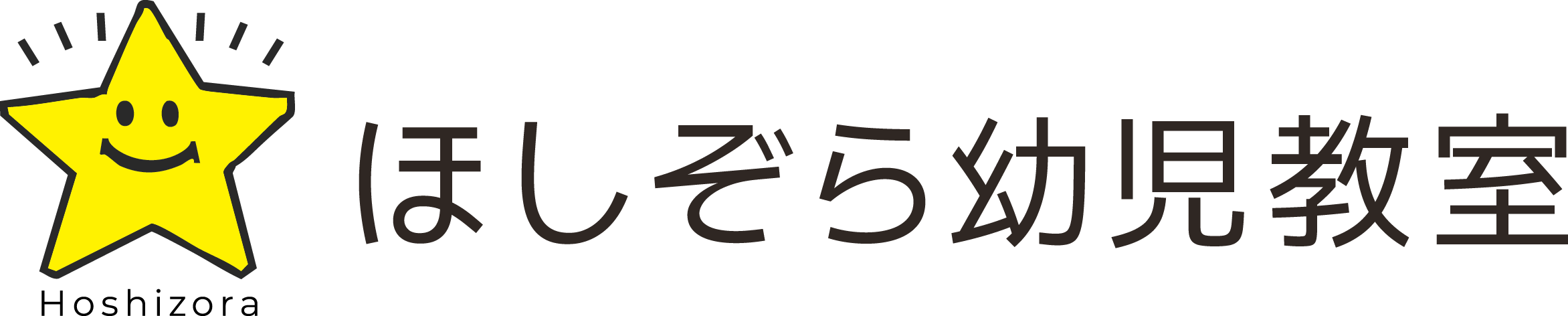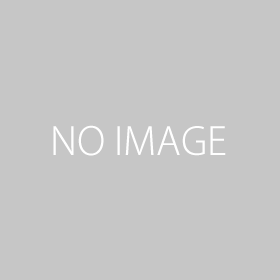こんにちは。ほしぞら幼児教室の講師、今井です。
先日、Xで「宿題しなさ〜い!」という内容の投稿をしたところ、思いのほか多くの方にご覧いただきました。
共働き家庭が増える中で、保護者の方が宿題の声かけに悩まれる場面が多くなっていることを、改めて実感しました。
宿題が進まない理由は「やる気」だけじゃない
宿題がなかなか進まないとき、つい「やる気がないのかな?」と思ってしまうこともあるかもしれません。
でも実は、子どもの発達段階や習慣、見通しを持つ力、そして失敗から学ぶ経験など、さまざまなことが関係しています。
自己効力感とは?〜「やればできる」と思える力〜
今日は、もう少し深く「自己効力感」という視点から考えてみたいと思います。
カナダの心理学者アルバート・バンデューラは、「自分にはある行動をうまくやり遂げることができるだろう」という感覚を「自己効力感」と呼びました。
例えば、「僕は勉強ができない」と言うとき、それは「いい成績が取れない」だけでなく、「勉強という行為そのものができない」と感じている場合もあります。
「やればできる」と思っていても、「その“やる”ことが自分にはできない」と感じてしまうと、行動に移すことが難しくなってしまいます。
自己効力感を育てるには「達成経験」がカギ
バンデューラによると、自己効力感を高めるためには「達成経験」が最も重要だとされています。
たとえ5分の取り組みでも、「できた!」という経験が積み重なることで、自信につながっていきます。
例えば、「100点を取る」という大きな目標を、「問題集を3ページ進める」という小さな目標に分けることで、達成感を得やすくなります。
もし、低学年のお子さまがその目標に挑戦される場合は、問題集の最初の1ページを親子で一緒に取り組むことが、気持ちの切り替えのきっかけになるかもしれません。
小さな一歩が大きな自信に
宿題に時間がかかる日もあるかもしれません。私自身も、子育ての中で何度も経験しました。
宿題に取り組む時間は、親子にとって“葛藤”の時間でもあるかもしれませんね。
お仕事や家事を終えて、ようやく一息つきたい時間に「宿題しなさ~い!」と声をかける。
それでもなかなか進まない…そんな日が続くと、ついイライラしてしまうこともありますよね。
けれど、それは、保護者の方が毎日、お子さまのことを大切に思い、真剣に向き合ってくださっているからこそだと思います。
スモールステップであったとしても「できた!」の積み重ねが、子どもたちの、「自分は、うまくやり遂げることができる!」という自己効力感を育て、将来の学びへの意欲につながっていきます。
今日は、こんな考え方もあるんだな…ということを、ブログを通してお伝えしたくて書かせていただきました。
参考にしていただけたら嬉しいです。