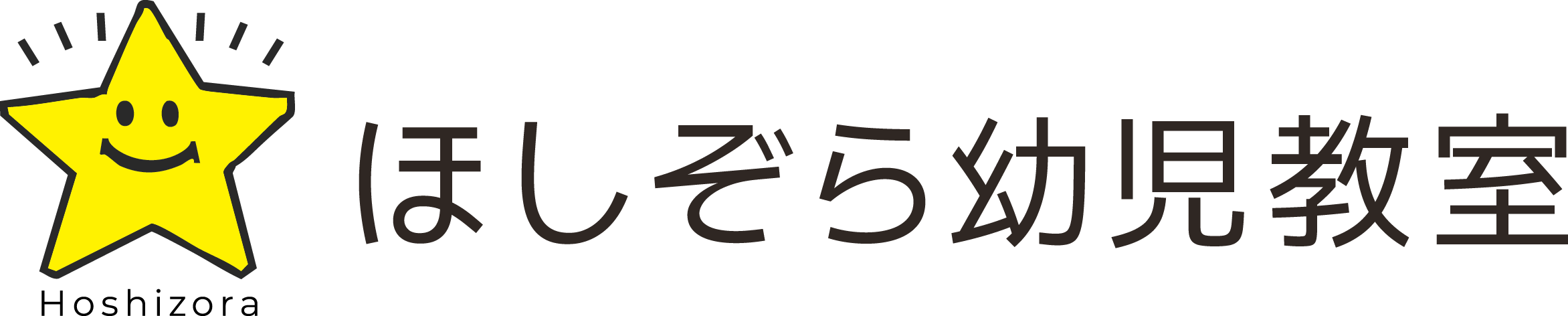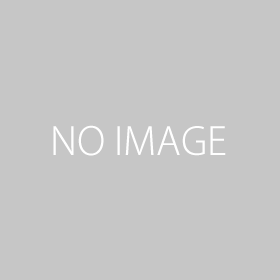こんにちは、ほしぞら幼児教室の講師を務めさせていただいている今井です。
今日は、長年の課題でもある「幼児期の育ちと小学校教育とのつながり」について、子どもたちの育ちを支える立場として、改めてじっくり考えてみました。
「安心感」が土台
乳幼児期の子どもたちは、保護者や身近な大人との愛情に包まれた関わりの中で、安心感を得ながら日々を過ごしています。その安心感があるからこそ、子どもたちは少しずつ自分の世界を広げ、行動範囲を伸ばしていきます。
この時期の子どもたちは、さまざまな事物や現象と出会い、好奇心や探求心を抱きながら、周囲の大人や友だちとの関わりの中で、遊びの成功体験や失敗体験を味わい、試行錯誤を繰り返していきます。
そして、互いに影響を受けながら育ち合う日々の中で、興味や関心はどんどん広がり、言葉を覚え、自分の思いを表現する喜びを味わいながら、さまざまな活動に挑戦するようになります。
こうした経験の積み重ねが、やがて思考力の基礎となっていくのです。
「遊びこむ」ことが「学びこむ」力につながる
幼児期の教育は、「環境を通したあそび」が中心です。
遊びは、子ども自身が選び、主体的に取り組むものであり、結果よりもその過程が大切にされます。
子どもたちは、見て、触れて、感じて、考えて…五感をフルに使いながら、夢中になって遊びこみます。
この「遊びこむ」経験こそが、のちの「学びこむ」力につながると考えられています。
遊びの中で育った好奇心や集中力、協調性、自己抑制などは、児童期の教科学習にもつながる大切な力です。
しかし、小学校に入学すると、生活の場や人との関わり方が大きく変わります。
「学校のルールを守る」「時間通りに行動する」「自分で考えて動く」など、求められる力が一気に増えるのです。
この幼児期の育ちと小学校生活のギャップが、いわゆる「小1プロブレム」と呼ばれる壁につながることもあります。
子どもが戸惑い、不安を感じてしまうのは、“できないから”ではありません。育ちの流れに沿った準備が十分でないことも考えられます。
新しい学びは、失敗からも生まれます。ちょっとした遊び心を取り入れて、創造性や洞察力を育みながら、問題解決を促していくことも必要になってきます。
子どもたちの「今」を見つめることが大切
幼児教育に携わる私たちや、保護者さま、小学校の先生方は、「子どもたちは今、どんな力を育てているのか」「どんな関わりが、安心感や自信につながるのか」を丁寧に見つめていくことが大切だと考えています。
具体的な関わりとしては、「言葉+動き」で伝えること、応答的に関わりながらゆっくり説明すること、活動に入る前に練習時間を設けること、ある程度ルールが分かってきたところで本題に入ること、大事なことは繰り返し伝えること、そして一緒に取り組むこと。
こうした関わりが、子どもたちの理解と安心を支える土台になります。
ほしぞら幼児教室における講師としての思い
ほしぞら幼児教室では、講師である保育教諭の役割を「育ちを支える専門職」として捉えています。
子どもたち一人ひとりには、それぞれ異なる育ちの道筋や個性を丁寧に受け止め、保育教諭としての専門的な知識を活かしながら、発達の過程に配慮し、その子らしさを尊重した関わりを大切にしています。
幼稚園・保育園を卒園して小学校に移行していくなかで、子どもたちは突然違った存在になるわけではありません。
発達や学びは、連続して積み重ねられていくものです。そのことを十分に理解した上で、子どもの学びを支えていきたいと考えています。
そして、「幼児教育」が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることを重要な課題として捉え、なるべく教育の段差を減らし、幼児期の育ちと小学校の学びがなめらかに接続できるよう、これからも子どもたちの育ちを丁寧に支えてまいります。
(参考:著者ピーター・グレイ、訳者吉田信一郎,『遊びが学びに欠かせないわけー自立した学び手を育てるー』,築地書館,2018年4月)
(参考:三好真史,『学校が大好きになる!小1プロブレムもスルッと解消!1年生あそび101』,学陽書房,2021年3月)